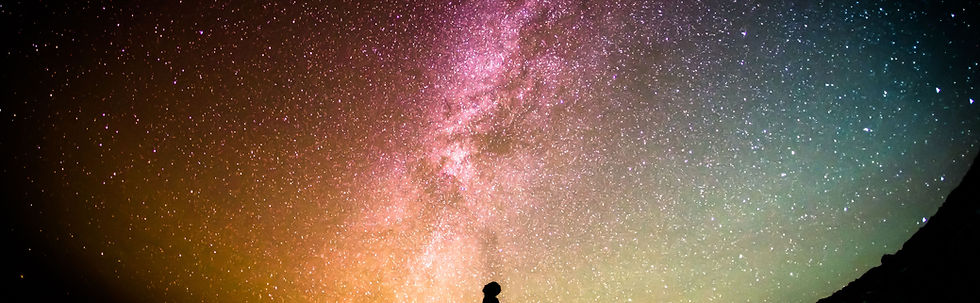
お正月シリーズ
「寂しさの埋め方」
*ユフィ視点です
あと数時間で年が明ける、十二月三十一日。
我がトルリットもまた夜遅いのに関わらず、城下は明かりと人で溢れているのが執務室の窓から見える。それを横目に、最後の書類に判を押すと両手を広げた。
「終わりました~!」
「お疲れ様ですわ、姫様」
なんとか仕事納め出来た私に、ジェリーが拍手してくれる。
傍にいたマオンちゃんも起き上がると脚に頬を寄せ、身を屈めた私も抱きしめた。
「マオンちゃん、終わりました~。これで一緒に年を越せますね」
『ギャウッ!』
「あらあら姫様、そういうのは旦那様に向けて言うものではありませんの?」
「え?」
苦笑の声に、ふさふさな鬣に埋めていた顔を上げる。
何を言われたのか一瞬わからなかったが、窓に映る自分の耳。琥珀のピアスに顔を真っ赤にした。
「ああああ、そ、そうですよね。普通はそうですよね。わ、私、結婚……したんですよね」
「ちょ、姫様、それ大丈夫?」
両手で頬を覆うと、ソファに座っていたランジュが転ける。向かいに座るワンダーもまた、豪快な笑い声を響かせた。
「なっははは! まだまだ新婚が故に実感がないのでしょうな」
「ていうか、肝心のルーファスもいないじゃん」
「ルーなら視察に出てますよ、ニ週間ほど前から」
「「「え?」」」
絨毯の上に腰を下ろした私は、マオンちゃんを撫でながら答える。
でも三人の目が丸くなり、小首を傾げると、順に疑問を投げかけられた。
「え、ちょ、ニ週間って……つまり姫様、ニ週間もルーファスと会ってないの!?」
「平たく言えば一ヶ月でしょうか……私も忙しくて」
「そ、それでも夜は一緒に寝てますわよね!?」
「いいえ。先も言った通り、互いに忙しい身ですので、ルーは団長室で休んでいます」
「な、なんと! 新婚夫婦が早くも離れ離れなど!! ああ、姫、お辛かったでしょう!!!」
「そんな、顔を合わせないことなんて今までもありましたし、たとえ会いに行っても『そんな暇あるなら仕事しろ、バーカ』って言われます」
「「「ああー……」」」
すぐに浮かんだのか、三人は大きく頷いた。
苦笑するしかないが、それほど忙しかったのも事実。今までと変わらない……はずなのに、いざ会ってないのか、辛くないのかと問われると急激に寂しくなってしまうのはなぜだろう。
忙しさから解放されたが故の不安。定期的に報告書は来ているので無事なのはわかるが、なんだか物足りなさを感じてしまう。立ち上がると、騎士団の予定表。ルーの帰城日を確認した。
「あ……!」
つい漏れた声に三人と一匹の視線が集まる。慌てて頭を横に振った。
「な、なんでもありません! わ、私、お茶とお風呂の用意を頼んできますね!! 三人もほどほどにお仕事を切り上げてください!!!」
(((今日、帰ってくるんだな……)))
視線が生暖かいものに変わったことなど知らず、私は大股で扉に向かった。
* * *
時刻は当に0時を過ぎ、新年を迎えた。
花火も上がる外とは違い寝室は静かで、扉は一向に開く気配はない。ずっと見つめていた私はぽてりと、クッションを抱きしめたままソファに転がった。
「ルー……帰ってきませんね」
マオンちゃんもいないせいか答えは返ってこない。
予定は予定。予定は未定。長旅ですし、どこかに寄ったり、誰かを助けてるかもしれない。彼にはその権限があるし、見た目に反して優しいところがある。私以外には。
「はふ……明日の新年祭の前に会えるで……しょう……か」
横になったのがいけなかったのか、徐々に瞼が重くなってくる。
でももう少し、もうちょっと待って……──。
「……く……て……たら……」
ブツブツと、小言を言っているような声が聞こえる。
とても馴染みがあって、反論したくて、必死に瞼を開いた。朧気な世界でも見えるのは綺麗な浅葱の髪。
「ルー……?」
「ちょうど起きたか。ヴァーカ」
「お帰……ひゃっ!」
不満そうな顔が見えると、放り投げられる。
まだ頭が寝ていたせいで悲鳴を上げてしまうが、柔らかいシーツに包まれた。サイドテーブルに灯るライトがなくとも、弾み具合でベッドだとわかる。困惑しながら見上げると、ルーは踵を返した。
「ま、待って!」
「なんですか?」
ピタリと足を止めたルーは振り向く。
けれど、咄嗟に呼び止めただけだったせいか言葉に詰まる。案の定、大きな溜め息を吐かれた。
「まったく、年明け早々ソファで寝るヴァカがいると思えば固まって……用がないなら失礼しますよ。明日も朝から祭典がありますし」
「ル、ルーはここで寝ないのですか!?」
慌てていたせいか上擦った声になり、ルーの目が丸くなる。
それでも真剣な眼差しを向ける私に口を開いた。
「ですから、明日も早いですし、シャワーも浴びてませんので」
「じゃ、じゃあ今日はもう一緒に寝て、明日の朝、お風呂に入りません!? せ、背中流しますよ! ふ、夫婦ですし!!」
止めようと必死になってか、自分でも何を言ってるのだろうと気付く。
でも、口から出てしまったことは消せないし、夫婦なのだから変じゃない……変じゃない、ですよね?
「顔を赤くしたり青くしたり、忙しい人ですね」
今の状態を的確に突かれ、両手で頬を覆う。
すると、溜め息をついたルーはマントもコートも脱ぎ、ネクタイを解きながら隣に座った。沈んだベッドにドキリとするが、無言でシャツボタンを外す彼にそっと訊ねる。
「お、怒りました?」
「いいえ。汗をかいた男が一緒でもいいという陛下の寛大なお心に感謝してます」
「そ、それ怒ってるじゃないですか!」
皮肉に肩を叩く。瞬間、手首を握られ身体が跳ねた。
すぐ目の前には一ヶ月振りに見る顔。好きを自覚してからは見つめられるだけで動悸が早くなって視線を逸らす。けれど顎を持ち上げられると口付けられた。
「ふぁ、ん……」
突然のことに驚くが、シーツとは違う柔らかな唇と優しい舌遣いに何も考えられなくなる。むしろもっと欲しくてなって、自分から唇を押しつけた。が、すぐ離されてしまった。
「あ……!」
寂しさと怒らせた、違う感情が入り乱れる。
恐る恐る見上げると、ルーは手の甲で唇を隠していた。やっぱりダメだったのかと私は肩を落とす。
「……に……いこと……でください」
「え?」
聞き取れるかどうかの小さな声に、つい顔を上げた。
その口元は隠れ、眉は吊り上がっている。怒っているように見える。でも、頬はどこか赤く、視線を逸らしたまま呟いた。
「勝手に……可愛いこと……しないでください。我慢……出来ないでしょ」
「え?」
聞き間違いか、それとも夢かと思える言葉を聞いた気がした。普段なら決して言わないし、言う人でもない。
でも、見たことある。愛を囁いてくれる時、私を……私を求めてくれる時の顔だと。
「……でください」
替わるように呟くと、ルーの目が私に移る。
今までだったら言葉の意味を理解出来ず流していたかもしれない。でも今はわかる。何より自分がそうで、ゆっくりと抱きしめた。
「我慢しないでください。いなかった分、いっぱいいっぱい愛して……私にも愛させてください」
「……ユフィ」
呼ばれただけで胸が高鳴る。
でも、琥珀の瞳に囚われたが最後。深い口付けを繰り返しながら押し倒されると、ナイトドレスを脱がされる。下着だけでは恥ずかしくて手で隠そうとするが、先にルーの手が乳房を荒々しく揉んだ。
「は、あ……」
「我慢するなと言ったのはお前だからな……加減出来ないぞ」
「はぃ……ああ!」
真っ直ぐな瞳と赤くした頬に笑みを浮かべれば、下着も脱がされる。
片方の乳房は揉まれ、片方の乳房は舌先で舐められ、片方の手が秘部を擦った。久し振りの感覚に微かな痛みを覚えるが、すぐ快楽へと変わる。
「あ、あぁん……ルー……」
「なんだ……痛いのか」
「んっ、あ……気持ち良い……の……もっと」
「……はい、我が姫君(ネ・プリンキピサ)」
くすりと笑う声がすると、ルーは股に顔を埋める。
次いで、秘芽を、蜜を舐め、卑猥な音を響かせながら吸い上げた。
「あ、ああああぁん!」
不安も寂しさも忘れさせるほど淫らで気持ち良い刺激。
止まることのない愛液を、ただルーは夢中にしゃぶっている。嬉しくて嬉しくて、私も何か返したくて彼の髪に手を置くと、視線だけが上げられた。
「わ、私にもルーの大きいの……舐めさせて……」
「いえ、さすがに私のは……」
「ちょうだい……」
シャワーしてないことに躊躇っているのがわかるが、逆に綺麗にしてあげたい、尽くしたい想いが強く、手を伸ばす。しばらくして観念したのか『失礼』と跨った彼は、ズボンからはち切れんばかりに聳り立ったモノを取り出した。
それは興奮している証だと以前ヒナタ様から聞いたことがあり指先で突く。それだけでルーは呻いた。
「あ、遊ぶな……」
「ご、ごめんなさい……あん」
互いに恥ずかしくなると、大きな肉棒が胸の谷間に挟まされる。
予想よりも大きくて硬くて熱いモノに、いったい中身はなんだろうと気になり、亀頭をカプリと咥えた。
「っ……!」
また呻いたルーは、寄せた乳房で肉棒を隠し、ゆっくりと腰を動かす。
離れていった肉棒を捕まえるように口を開くが、かろうじて唇につくか、舐めれるだけで、中々咥えることが出来ない。なのにルーは息を上げている。つまり気持ち良いのだと、両手で持った乳房で肉棒を捕まえると、亀頭だけでなく、奥まで咥え込んだ。
「あ、あぁぁ……!」
歯を立てないよう、吸っては舐める。
ルーが自分にしてくれたように恩返しするように速度を速めると、口内で膨張するのを感じた。
「っ……ユフィ……悪いが……出る」
「ふぇ……っ!?」
懇願するような声に顔を上げると頭を押さえられる。そのまま熱く、いいようもない粘り気のあるモノが放出された。引っこ抜くと、両手で口元を押さえる。
「んっ、んん~……なんですかこれ」
「精液」
「せっ……ひゃ!?」
淡々と言われ驚くが、ゴックンと飲み込むと同時に両脚を屈曲させられる。そのまま焦らすことなく挿入された。
「あ、ぁぁあああ゛っ!」
先ほど出したと思ったのに、ナカを掻き回すモノの大きさは変わっていない。
なんでと思う暇もなく覆いかぶされると、結合部は深くなり、最奥をガツガツと突かれた。
「あ、あぁん……ルー……激し……大きんん!」
「一ヶ月も顔を見ないようしてたん……ですから……しょうがないでしょ……明日が終われば……休暇だったのに……貴女が煽いだせいで……っ!」
「ひゃっ、あぁあああああっ!!!」
まるでワザと会わなかったのにと言うように、抱きしめられたまま奥を突かれる。いつもの余裕は欠片もなく、ただ感情のままに、男という獣になって犯す彼に不思議と歓喜した。容赦なく繰り返される抽送は我慢の、自分を求めている証だと、薄れる意識のなか抱きしめると口付けた。
「ルー……好き」
「愛してる……」
すれ違いが多ければ多いほど深くなる寂しい穴。
けれど、貴方の想いが簡単に満たしてくれる。女王と騎士ではない、愛する人だから──。
翌日、自分で言っておきながら恥ずかしいお風呂に一緒に入浴。
尽くすように洗ってくれたがどこか意地悪で、痛む腰を堪えながら新年祭に出席した際は『蟹股女王』と称される始末。
もう、ルーなんて知りません────!
